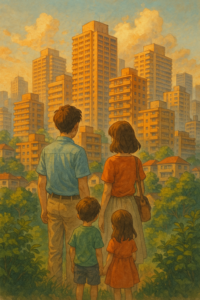勤務医で大学病院勤務、30代~40代、子どもが2~3人いる状況を想定して考察します。独身や子ども1人の家庭と、子どもがたくさんいる家庭では、資産形成の難易度がかなり異なるためです。
Contents
子どもの教育費がエグい
都内では、おそらく小学校進学前から教育費がかかり始めます。地方都市でも、小学校、中学校、高校と進学するにつれて教育費は上昇していきます。
私自身は中学、高校まで公立に通っていたので、「子どもは育つように育つ。塾は不要」派でしたが、今そのような考え方の医師は少数派だと思います。ある程度の年齢になったら私立学校に入学させて、高校受験を経て可能なら医学部入学を目指すという過程が大多数かもしれません。
その道を選択した場合、教育費はエグいですね。特に私立大学に進学すると、支出が跳ね上がります。
生涯現役が大前提
今からの社会は、死ぬまで働くのが基本設計になります。死ぬまで働くと聞くと、なんだか憂鬱な気持ちになりますが、少し言い方を変えて「死ぬまで社会に貢献するスキルを発揮し続けて、社会と接点を持ち続ける」と考えるのが良いかもしれません。
稼ぐイコール労働ではありません。お金を稼ぐ手段は、株式投資でもいいし、不動産投資でもよい。幸い、医師の仕事、特に外来については、高齢になっても続けやすい仕事の代表格だと思います。
子どもが大学を卒業したタイミング、おそらく自分の年齢的には50代~60代以降は:
- 労働収入は少しずつ減少させていく。当直バイトなどは相当にきつくなる年齢です。でも、細々とでも収入を維持することは大切
- 多くの医師にとって、生涯医師として働き稼ぐというのが、社会への貢献とそれに見合った報酬を得るという意味で最適解な気がします
もちろん、高齢になった自分が医師として社会に貢献するよりも、もっと別の適性があるというならそれも全く問題ありません。たとえば事業を経営するとか、不動産で規模拡大するとか。
ただし、医師の活動を0にして不動産100にすると、社会との接点が希薄になって朝からお酒を飲むような生活になりそうな気もします。逆に、医師として週に何回か外来をしながら不動産経営というスタイルは最高かもしれません。
30代~40代の資産形成戦略
上記は出口戦略。資産0の30代~40代に話を戻します。
人生において、お金はとても重要ですが、お金だけを目的に人生設計することは危険です。資産形成は、上を見だすときりがない。男性医師と非医師のパートナーで、大学病院勤務を想定した場合、子ども3人を全員私立に行かせるというのはかなりの無理ゲーとも言えます。
ところが、子どもは全員公立でいいやと割り切ることで、人生設計はかなり楽になります。私自身も大学に進学する時点で、家庭環境から私立大学に進学する道は0でしたが、それをマイナスに捉えたことはありません。大学まで公立のみ。あとは自分で頑張れ!という思い切った割り切りは意外に重要かもしれません(パートナーの同意を得るのが結構難しいかもしれませんが)。
逆に、私立に進学させられるのは子ども1人だから子どもは1人で我慢するというよりも、よほど子だくさん家庭の方が良い気がします。子どもの数は、自分が欲しいと思ったらたくさん生んで育てるというのが、長い人生を考えると良い気がします。
人的資本の重要性
大学病院もしくは公的病院に勤務していると仮定した場合:
- 家族と過ごす時間(旅行なども含む)
- 病院で自分のスキルや学会での認知度を含めた、勤務医としての位置エネルギー
- お金(資産形成)
これらを考えたとき、なかなかお金にまで気が回らない気がします。
子どもが小さいころの時間というのは、長い人生を考えたときにかけがえのないものですし、資産形成を終わらせてから後から取り戻すことはできません。人生にとって人的資本(友人、ビジネスパートナー、家族)も非常に重要なので、この時期は人的資本を積み上げることに専念するのが良い気がします。
家族と過ごす時間を優先する。学会などに積極的に出かけて、知り合いの医師を増やす。自分の所属する病院の外の世界で、自分の価値を高める。自分の所属する病院で「あの人いい先生だね」というのも大事ですが、転勤するとその資産を持ち運ぶことはできません。
でも、学会などの重鎮やオピニオンリーダー、同年代の世代に「あの先生は頑張っている。すごい!」という認知を得ると、その価値(錯覚資産、他人の脳内に蓄積する資産)は生涯にわたって利用可能です。勤務医としての価値は、自分の所属する病院だけでなく、外部の病院、クリニックに所属する医師の脳内に蓄積するというのは大事な考え方です。
30代~40代の具体的な資産形成
この時期は、家族との時間、自分の人的資本(働いて稼ぐ力)、社会資本(人とのつながり、錯覚資産)を高めるのが良い気がします。とはいえ、資産形成に無関心ではいけません。
5%くらいのリソースでもよいので、資産形成は続けましょう。まずは家計簿を作る。家計簿につける項目は、総資産、1ヶ月間の収入(主には勤務先、アルバイト先からの給与)、固定費の出費くらいで良いと思います。株式も記載。ダイエットで重要なことは毎日体重計にのり、記録をつけること。資産形成においても、毎月家計簿をつけて、総資産を把握することが重要です。
ひとまず、この時期は資産形成に割けるリソースが少ないので、NISAを少額からスタートすると良いと思います。少額で良いので、自分の労働収入(給与)以外の収入源を持つこと、体験することが大事です。
そして「自分の総収入に占める、労働収入以外の割合」を時々計算してみましょう。最初は0もしくは数%だと思います。ここから、給与以外の収入割合を少しずつ増やしていきます。
目指すべきゴール:給与依存度49%以下
1つの目指すべきゴールとして、「総収入に占める給与の割合を49%以下」にすることを目指しましょう。これは、私が若かりし頃に知り合いから教えてもらった大事な考え方です。
給与の割合が49%以下になるということは、「医師を辞めて、医師以外の収入を上げた方が合理的」となります。私の知り合いには、勤務先の給与所得の割合が8%以下(たぶん今はもっと少ないと思う)という人がいました。その人は、すでに勤務先を辞めて他の事業にコミットした方が総収入は増えるという状態ですね。今も勤務は続けていますが、いつ職場を辞めても問題ない状態。ここを目指すのが良いと思います。
そして大事なことですが、人生100年時代&死ぬまで働き続ける(稼ぐ≒社会との接点を持つ)を前提とするなら、給与の割合が49%以下に到達するのは50歳でも70歳でも良いということです。
その人にとって、勤務先でコツコツと働くことが苦痛ではないなら、70歳になった時期であっても労働収入への依存度が70%とかでも全然問題ないと思います。ただし、人間はいつかは働くことが難しくなるので、労働収入以外を少しずつ増やすという考え方は持っておきましょう。
当然ですが、労働収入の割合が49%以下になった瞬間に職場を辞める必要はありません。医師という仕事は、人から尊敬される仕事(最近その意味が少しずつ失われてはいますが)であることに変わりはありません。私の知り合いの不動産経営をしている人からはいつも、「不動産経営は儲かるけれども承認欲求は全く満たされない」と言っています。人の役に立つこと、承認欲求を満たすことはわりと大事です。
労働に依存しない収入を少しずつ増やす
30代~40代のころは、労働収入に100%依存した状態からスタートします。そこから株を買ったり、スモールビジネスをしてみたり、不動産購入の勉強をしたり。少しずつ労働収入に依存しない収入を増やします。
ここで大事な考え方として、必ずしも1つの収入に依存しなくてもよいということです。もちろん、医師以外には不動産投資にフルコミットするというのもありです。でも、不動産投資の代わりにREIT(不動産投資の株版みたいなものです)を選択して、他に複数のスモールビジネスを展開するというのもありです。
労働収入以外の収入源というのは、最初は細い収入源です。これを複数束ねて、少しずつ大きな収入源にしていくのが良いでしょう。
人生の後半には、自分が労働者として稼ぐ力が頭打ちになり、下降し始めます。若い頃は外勤で当直のアルバイトもさほど苦でなかったとしても、だんだんきつくなります。その頃から、医師として働いて稼ぐ以外の収入源を複数所有し、その金額がだんだん増えていく状態を目指すと、バランスがよくなるでしょう。
法人設立による効率化
その過程では、どこかの段階で合同会社を設立するのが良いです。いわゆる法人を所有して、効率よく稼ぐ(節税する)ということです。働いて稼ぐ金額を増やすと、累進課税により税金が増えます。つまり、自分の収入が労働収入1択だと、お金が足りない→働く時間を増やす→それに伴って税金が増えるので効率が悪くなるといえます。
バケツに大きな穴が空いた状態で水をすくっている状態です。給与所得については節税の方法が限られており、逃げ場はありません。でも、医師以外の収入については、法人所得にすることで節税が可能になります。
税金というのは、長い目で見て資産形成の速度を下げる大きな要因になります。この税金という足かせを外せると、資産形成の効率、スピードがアップします。